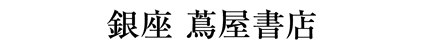ヤノベケンジ・米山舞対談「アートとアニメーション、アナログとデジタルをボーダレスに横断する二人のアーティストによる夢の共作と新たな挑戦」
2023年7月から開催され、“SESSION”をコンセプトに、様々なアーティストの表現が交わり、アートに親しんでもらうアートイベント“ART SESSION”が3回目を迎える。今回も、GINZA SIX6階にあるアートと日本文化の書店「銀座 蔦屋書店」内中央イベントスペースGINZA ATRIUMを中心に展示される。
世界各国を拠点に第一線で活動を続けるアーティスト、日本美術のアップデートを試みるアーティスト、気鋭の若手アーティスト、さらにストリート、ファッション、グラフィックといった多様なカルチャーをバックグラウンドに持つアーティストが一堂に会する挑戦的な試みでもある。
そこで、“ART SESSION”では初の試みとして、まさに “SESSION”をテーマに、2名のアーティストによる共同制作の作品を発表する。2024年春よりGINZA SIXの中央吹き抜けに宇宙船から猫が炸裂する巨大インスタレーション《BIG CAT BANG》を公開して大きな話題となっている現代美術作家・ヤノベケンジと、ロンドンのサーチギャラリーで開催された「START ART FAIR 2021」にも選出された、日本を代表するアニメーター・イラストレーターである米山舞によるコラボレーションだ。

2024年4月からGINZA SIX中央吹き抜けに展示されている《BIG CAT BANG》
撮影:Yasuyuki Takaki
撮影:Yasuyuki Takaki

「ARTIST FAIR KYOTO 2024」に選出された米山の作品展示風景
米山舞とヤノベケンジ、世代もジャンルも違う異色の二人のコラボレーションがどのようになるのか?米山のスタジオで制作中のヤノベと米山に話を聞いた。
●二人の初めての出会いとウルトラファクトリーという創造の現場
昨年、渋谷PARCO 「PARCO MUSEUM TOKYO (パルコミュージアムトーキョー)」で催された米山の個展「EYE」では、眼や表情の動き、変化によって動かされる感情をテーマに、イラストレーションや映像作品だけではなく、立体的な手作りの作品も発表された。
実はそれらの作品はヤノベがディレクターを務める京都芸術大学ウルトラファクトリーの協力によってつくられたものだという。どのような経緯で二人は出会ったのだろうか?
実はそれらの作品はヤノベがディレクターを務める京都芸術大学ウルトラファクトリーの協力によってつくられたものだという。どのような経緯で二人は出会ったのだろうか?

東京渋谷PARCO MUSEUM TOKYOで開催された米山の個展「EYE」会場風景
撮影:株式会社カロワークス
撮影:株式会社カロワークス
ヤノベ:「米山さんと初めてお会いしたのは、ウルトラファクトリーに見学に来られた時なんです。アニメーター、イラストレーターとしてすでに活躍しているのに、自分の分野とは違うものづくりの現場を見て、ここに住み込んでつくってみたいとおっしゃった。そういう垣根も越えて、創造しようとする挑戦的な精神にすごく魅力を感じました。キャリアを積んで大成すれば、そこに留まって安定しようとする人が多い中で、SSSのようなイラストレーションのチームを組みながら、業界自体を変えていくパイオニア精神も持っている。だから、それはもうぜひ使ってくださいということで話は進みました。」
米山は、実はヤノベが勤める京都芸術大学の通信教育学部のイラストレーションコースの講師や広報ビジュアルなども担当していた。ちょうどアンテルーム京都で米山が所属するイラストレーター集団SSS by applibotのメンバーと京都の伝統工芸の職人とコラボレーションした展覧会「SSS Re\arise」を開催していたこともあって、京都芸術大学の施設を視察していたのだ。
米山:「通信教育部のキービジュアルを担当させていただいた関係で、その担当の方にぜひ寄ってみないかとご提案いただきウルトラファクトリーさんを案内いただきました。そこでどのように作品制作に向き合い活動をしているかを目の当たりにして、リスペクトを持ちましたし、自分も創るのであれば、このぐらいやりたいな!という気持が強くなりました。何より沢山の未知の設備や道具があってワクワクしたんですよね。作品にはプロセスが大事だと思っているので、創りたいって言っているのに自分は現場にはいない、というのが想像できなかったんです。職人的なものも好きだし、そういうスピリットが自分にもないといけないなと思っていて、とにかく物を創ることに憧れたんですよ。デジタル上でのイラストレーション表現や、IP(Intellectual Property、知的財産)をチームでやらせて頂いてきた経験はあるのですが、自分の感性をアナログ作品として反映させたらどんな出力になるんだろう?という単純な興味が湧いてきたんです。」

撮影:野﨑航正
京都芸術大学のウルトラファクトリーは、どこの学部・学科の学生も使用することができる大学の学部を超えた共通工房として2008年に開設された。その設立から現在までディレクターを務めているのがヤノベだ。
ヤノベは、1990年代から活躍する現代美術作家で、村上隆や奈良美智などと並び、漫画やアニメ、特撮映画といった日本の戦後のサブカルチャーで育まれた美学をいち早く現代アートの世界に取り込み、国際的な評価を得た。1997年には自作の放射性感知服《アトムスーツ》を着用して原発事故後のチェルノブイリ(チョルノービリ)に訪問するなど、個人的な経験と社会的なテーマを結びつけた作品群は、美術史家、ブランドン・テイラー(現・サウサンプトン大学名誉美術史教授)による『Contemporary Art:Art Since 1970』(プレンティス・ホール、2005年)など、海外の美術書にも多数掲載されている。
近年のヤノベの代表作である《サン・チャイルド》(2011-2012)や《サン・シスター》(2015)、《ラッキードラゴン》(2009)、現在も続く《SHIP'S CAT》(2017~)シリーズに至るまですべてウルトラファクトリーで制作された。それだけではなく、世界の一線で活躍しているアーティストやクリエイターを招聘し、実践型の教育プログラムとして数多くのプロジェクトを実施している。ヤノベも過去にはビートたけしや明和電機、増田セバスチャンなどと多くのコラボレーション作品を制作している。

左《サン・シスター》撮影:KYAP 右《サン・チャイルド》撮影:藤木潤一
ヤノベ:「米山さんの申し出には、多少びっくりはしましたが嬉しかったですね。ウルトラファクトリーは、クリエイターの坩堝(るつぼ)として、プロやアマ、学生を含めて創造のエネルギーをぶつけながら大学の内燃機関になり、京都や日本を前に回転していく。そのエネルギーの塊にいろんな人が惹きつけられたらいいと思ってやってきました。住み込んででもやるみたいな強さ、そこには分野を超えて、クリエイティブなエネルギーの根源を追い求めている姿勢を感じました。だから米山さんが来たら、若い学生も感化され、逆にウルトラファクトリーを新しい次元に連れて行ってくれるんじゃないかという期待もあったんです。」

撮影:野﨑航正
ヤノベは米山の心意気に惹かれ、米山が制作できる体制を整えたという。
ヤノベ:「スタッフや学生にも声かけて、失礼のないように、学生には必要になる技術的なことを習得させました。学生にしたら米山さんは神様のような存在だったので、そういう人を迎え入れる環境を整えて、一緒に制作に携わった学生は、人生観が変わるくらいの経験になった。米山さんは、自分が物づくりに向かう姿勢を含めて、学生たちの面倒も見てくれました。」
米山:「実はプレッシャーを感じていた部分があって、他のプロジェクトがある中、スタッフさんも入ってくださっていましたし、最初は本当にやるんですか?みたいな感じの空気が漂っていて(笑)、私も本気を見せないといけないと思ってやっていたんです。それでも次第に理解していただき、いろんな出来事を経ていざ作品が出来上がり、展覧会が始まって……。レセプションにみなさんが来てくださったんですけど、顔を見た瞬間になんだか感極まってしまいました(笑)……でもそれくらい、想いが込められた創作活動を私ひとりだけじゃなくて、皆さんとすることができました。」
渋谷PARCOで開催された展覧会「EYE」では、米山は直前ともいえる約2か月間、京都に滞在しながらウルトラファクトリーに通い詰めて制作した作品を出品した。今まで米山は、SSSのメンバーらとイラストレーションの展覧会を開催したり、アクリル板や発光体を使った重層的な作品を制作したことはあるが、ウルトラファクトリーのようにすべて自分たちの手仕事で制作したり、すべてアナログによる制作はしていなかった。「EYE」に出品したアクリル板を複雑にカッティングして組み合わせた大型作品《JOY-RGB》や、3Dプリンターで出力したFRPや湾曲したアルミニウムを貼り付け、カンヴァスへ着彩したレリーフ状の作品《EYE》は、さまざまな素材をアッサンブラージュしたような手法である。また、はじめてシルクスクリーンによる版画作品も制作した。展覧会直前の試みとしてはかなりの冒険だといえるだろう。なぜそのような挑戦をする必要があったのだろうか?
米山:「ちょうどSSSでも自分でも個展をするようになって、自分がUV印刷を始めた頃からイラストレーター界隈の展覧会に対して、コレクターも増えたこともあってか作品の価値が上がって“プチバブル”みたいになっていたんです。でも表現方法や印刷方法がシステム化しすぎると肝心の中身が表現的に頭打ちになる気がしました。だからもっと自己表現に近づけたかったんです。イラストレーションは、IPやクライアントのためのものだったりするけど、自分のためのイラストレーション、人のためのイラストレーション、物を受け取るためのイラストレーションがどうかと考えたときに、印刷だけだと物足りないと感じました。それでどういう飛躍の仕方があるか考えていて、別の方向からのアプローチがあるとまた新しいイラストレーションの楽しみ方や見え方が出来るのではないかなという気がしたんです。」

米山とULTRA FACTORYスタッフとの打ち合わせの風景
しかし、極めて短い時間の中で、今まで自分がまったく使用していない素材や方法を選択し、展覧会に出品できるクオリティを見極めるのは至難ともいえるがそれはどのように行われたのだろうか?
米山:「何か課題があるとヤノベさん含めチームの方々が毎回対策を練ってくれたんです。いろんな側面からの知見や知識がおありなので、実現したいことに対して何をどうしたら良いのかのアドバイスをくださいました。
例えば半立体の作品《JOY-RGB》は、当初の予定では下地を描く予定だったのですが、他の素材のバランスを見て印刷に切り替えて他の部分に時間を費やすのはどうか、とか。レリーフ状の作品《EYE》も、FRPにする部分、3D印刷にするところの検討に大きな助言をいただいたり、作業に関しても切削にするものは分けてやった方がいいことや、各工程のスケジュール感なども教えてもらったりと、あらゆる面で学ぶことが多く勉強になりました。」
例えば半立体の作品《JOY-RGB》は、当初の予定では下地を描く予定だったのですが、他の素材のバランスを見て印刷に切り替えて他の部分に時間を費やすのはどうか、とか。レリーフ状の作品《EYE》も、FRPにする部分、3D印刷にするところの検討に大きな助言をいただいたり、作業に関しても切削にするものは分けてやった方がいいことや、各工程のスケジュール感なども教えてもらったりと、あらゆる面で学ぶことが多く勉強になりました。」
ヤノベ:「僕というよりも、スタッフのサポートが大きかったと思います。立体にする方法とか、かかる時間とか、どういう形なら具体的にイメージを表せるか、スタッフが楽しみながらやってくれたのが大きいですね。」
●壮大なストーリーを描くヤノベ作品の中に見出す、米山の感覚と未来
イラストレーション・アニメーションとアート、平面と立体、デジタルとアナログ、一見全く違ったジャンル、制作方法に見えるが、米山はヤノベの作品をどのように思っているのだろうか?
米山:「スケールがとんでもないなと思います。スケールといえば特撮やアニメをすごく理解されていて、よく見ると学生さんからも聞きました。ご自身が触れた文化、実体験に、未来に対する考えを織り交ぜながら凄まじい造形力で作品を創り出す。威厳がありながらもその中でポップカルチャーが混ざっているところがアートとして受け手に接点をつくってくれているんじゃないかなと思います。」
実際、ヤノベはポップカルチャー・サブカルチャーから多大な影響を受けたアーティストで、そういう意味では、表現の分野や方法は違っていても、ルーツとなる部分は共通しているといえる。まさにその日本のアニメーションの表現の第一線でやってきたのが米山である。ヤノベは漫画やアニメのように作品制作にあたって、コンセプトというよりも、キャラクターやストーリーをつくることが多い。その点、米山は自己表現する場合、どのように考えているのだろうか?
米山:「自分の中のストーリーというよりは、そのときに思うこと、日記っぽいです。自分が生み見落としている、古くなっている組織みたいなイメージでやっています。原作や監督をしないかと言われることもありますけど、表現したいことの中に物語があるというよりは、自己表現ですし、短い時間なんです。今の時代的にも、短く訴えかける方が合っている感じですよね。だから長いのをつくるにしても短いシーンのオムニバスとか、感覚的なものになると思います。お話はプロがいっぱいいるので、そこに挑むよりは自分の感覚を優先した方が面白いものができるんじゃないかと思っています。」

ロンドンのサーチギャラリーで開催した「START ART FAIR 2021」に出品した作品で米山は高い評価を得た。
今回、米山とヤノベのコラボレーションは、ヤノベが制作している《SHIP'S CAT》のシリーズと2015年に制作され兵庫県立美術館前に恒久設置されている《サン・シスター》をモチーフにしたものだ。
《SHIP'S CAT》シリーズは、2017年からは、福を運ぶ「旅の守り神」として、古代から人間と一緒に旅をし、ネズミなどの害獣から船体や船員を守った「船乗り猫」をモチーフにした彫刻で、大阪中之島美術館をはじめ、国内外の多くの施設や展覧会、芸術祭に巡回したり、恒久設置されたりしている。《BIG CAT BANG》は宇宙と生命の誕生をテーマにした発展形である。《サン・シスター》は阪神大震災20年の節目につくられたモニュメントで、東日本大震災の復興を願って制作した《サン・チャイルド》のお姉さんのような存在であるとしている。
実は、今年の春には清水寺で開催された「ARTISTS' FAIR KYOTO 2024」で、《SHIP'S CAT》が鏡のような太陽を運ぶ《SHIP'S CAT(Sun Carrier)》(2024)の映像を米山が担当しており好評を得ている。その際は、米山は《サン・チャイルド》と《サン・シスター》が希望の光である太陽を受け渡すアニメーションを制作した。

《Sun Carrier》撮影:表恒匡
今回、ヤノベのつむぐキャラクターやストーリーの中に米山は何を投影したのだろうか?
米山:「表現とか、立場とかに対して、未来を見出したいなって思っていいます。ジャンルが細かく分けられたり、それによって売り方が変ったり、そういうことに対しての疑問も多くあります。自分がアートや手作りみたいなものに挑んだらどうなるか考えたんですけど、迎合する必要はないし、自分の新しい表現に光を見出したいなと思ったんです。《サン・シスター》も希望がテーマになっているので、タイトルは、《サン・シーカー(Sun Seeker)》、追求者、探索者とさせてもらいました。今回、コラボレーションの話をいただいて、何案か描いたんですけど、ヤノベさんもこれがいいんじゃないか、と。単純にヤノベさんがマテリアルをつくって組み合わせるっていうだけだと弱いし、ヤノベさんのキャラクターだけど、それを自分なりに解釈する方がいいんじゃないかと思いました。」
今回のコラボレーションでは、ヤノベがつくりだしたキャラクターやストーリーを米山が解釈して新たな創造物をつくり、それを見てヤノベが彫刻部分をつくるという、かなり複雑な交流をして制作している。

撮影:野﨑航正
ヤノベ:「米山さんとのコラボレーションは、僕がオーダーしたストーリーやキャラクターに沿って何かしてほしいわけじゃないんです。米山さんのイマジネーションと画力に圧倒的な素晴らしさがあるので、それによって、今まで考えたストーリーとかつくり方とは全然違うところに連れて行ってもらえる期待があります。僕の作品の印象から生まれた新しい米山さんのイマジネーションを見てみたい。《サン・シスター》から発生しているんだけど、僕ではつくれない「ミューズ」を描いてくれていて、僕が今までつくった《SHIP'S CAT》とか《サン・シスター》とは違う次元に引っ張られていく面白さがあるんです。だから、これは僕の《SHIP'S CAT》とは、全く違う作品として成立するんじゃないかと思いますし、多分そうなると思います。その扉を開ける機会になる。」

共作の制作イメージが何パターンも描かれている米山のアトリエの風景 撮影:野﨑航正
●美術表現としての歴史的な関係と可能性
確かに米山が描いた今回の構想スケッチは、ヤノベのタッチとはまったく異なる、曲線と動き、女性の表情の変化を捉えたものだ。ヤノベは、その際、イタリアの未来派のウンベルト・ボッチョーニやジャコモ・バッラの《鎖につながれた犬のダイナミズム》(1912)、マルセル・デシャンの《階段を降りる裸体NO.2》(1913)、映画技術の元になったエドワード・マイブリッジの連続写真などを見出している。
確かに米山が描いた今回の構想スケッチは、ヤノベのタッチとはまったく異なる、曲線と動き、女性の表情の変化を捉えたものだ。ヤノベは、その際、イタリアの未来派のウンベルト・ボッチョーニやジャコモ・バッラの《鎖につながれた犬のダイナミズム》(1912)、マルセル・デシャンの《階段を降りる裸体NO.2》(1913)、映画技術の元になったエドワード・マイブリッジの連続写真などを見出している。
ヤノベ:「僕は彫刻作品をつくっていますが、米山さんはアニメーションのキャリアから入っているので、物をちゃんと立体的に、構造的なものとして捉えている。そこも僕もそういう勉強にはなっています。」
米山:「頭に全部入っているというわけではないんですけど、フローというか、流れみたいなものを意識はしているんです。そこを使わないと動いたときに全部止まって見えちゃうんです。いろんな向きで絵を描けるというだけじゃなくて、フローを意識した絵が描けるかどうか、ということなんです。意外と言及はされていませんが特殊技能だと思います。」

手描きのスケッチやカンヴァスが壁一面に広がる米山のアトリエ風景 撮影:野﨑航正
さらに、米山は日本で発展したアニメーション=アニメならではの技法を意識しているという。
米山:「日本のアニメーションは、欧米との大きな違いは、リミテッドというか、少ない枚数で表現することによって、どこが一番いい絵なのか、ポイントなのかを表す引き算的な魅力があると思います。引き算したときに、おばけ表現といわれる残像や、エフェクトが外国とは異なる表現だと思います。昔からある雨を線で描いたりするような、目に見えない光や炎、気体のような表現を線とか形でするんですけど、自分が育ってきたガイナックスとかトリガーとか、漫画表現をアニメに取り入れているところが、手塚(治虫)さんとかとも通じていて好きですね。」
それは浮世絵のような明治時代以前の日本の美術表現にも通じるものではないだろうか。そのようなことを感じたことはあるのだろうか?
米山:「ありますね。その時代によってデフォルメが違うところとかもすごく通じるんですよ。昔の浮世絵を見ても、写実的にはこんな顔のはずはない!とか思うじゃないですか。瓜実顔のような。でも、今のデフォルメされたアニメ造形を100年後に見てもこんな顔している人いるわけない、となると思うんです。そこは同じじゃないかと思います。でも当時の人はめっちゃかわいい、美しいとか思いながら描いていたと思うんです。」
その辺の洞察は、アニメーション、イラストレーションをやっている米山ならではといえるだろう。いっぽうで二人はアート、美術作品としての表現に対してどう思うのだろうか?
ヤノベ:「美術はアートマーケットの世界がある一方で、長い時間軸で存在できる一つの分野だと思います。だからそれこそ米山さんのような非常に優れた感性とそのキャリアと知識を持っているクリエイターの作品は、100年後200年後あるいは1000年以降にきちっと見てもらえるために、美術という枠組みの中で残すのは一つ役割があると思います。だから今回のコラボレーションも、米山さんが歴史的に、あるいは世界の中でもきちっと存在感を見せるような美術作品がつくりあげられると思っているし、実現したいと思っています。」
米山:「ヤノベさん、有難うございます。残すという話でいうと、映像になったときに動く嬉しさみたいなものは、共通のものだと思うんです。特にSNSみたいな時代になると、共感したり多くの人の心を動かしたり、インプレッションがあるし、即効性もある。今の時代の価値観ならではの良さもありますね。それに対して立体の美術作品は、自分と向き合った時間が長くて、それに対する考えを巡らし、最終的に自分が生み出して残すという点では、ヤノベさんと美術作品を制作することでまた違う扉を開いてくれるものだと思っていて、それによってどんな世界が広がっていくかが楽しみです。」

対談の終わりにヤノベ、米山の二人で共作のラフスケッチとともに 撮影:野﨑航正
実は戦後、日本では華族の廃止や財閥解体、農地解放、あるいは累進課税や相続税などによって資産家が極端に減って、総平民化した経緯がある。そのため、戦前にあった上流階級のハイカルチャーとしての美術市場やコレクターは縮小し、その代わり大衆文化の中に、才能や資金が流れ込み巨大な産業、市場となって、今日に至る漫画やアニメ、特撮といったポップカルチャー、サブカルチャーのコンテンツが花開いた。そして、優れたコンテンツとなった日本の漫画やアニメは、世界の大衆文化にも浸透していく。
冷戦終結後、世界が開かれ、新たにグローバリズムが台頭する。そして大きく広がるアートマーケットの中で、日本の漫画やアニメの認知を活かして、それらのエッセンスを欧米の上流階級のハイカルチャーだった現代アートに取り入れたのが村上隆や奈良美智、そしてヤノベの世代である。今日では、グローバリズムが進行し、欧米圏だけではなく、アジアやアラブのアートマーケットも拓け、日本にも新たな富裕層が台頭している。そこでは全く異なる嗜好を持つコレクターも増えている。そこにおいて、日本の伝統工芸やサブカルチャーは大衆文化を経た新しい美術作品になる可能性を秘めているのだ。
漫画やアニメなどを創作するクリエイター、漫画やアニメの要素を取り入れるアーティストは、日本の大衆文化という共通の土壌の中で育まれてきた。だからヤノベのような現代アートの中でポップカルチャー・サブカルチャーを取り入れるアーティスト、米山のようにアニメーションやイラストレーションから始まって、美術作品を発表するクリエイターは、異色の出会いのように見えるが、合わせ鏡のような存在であり、共同制作も歴史的必然ともいえる。
さらに可能性があるとすれば、長編漫画やアニメのような大作、ストーリーではない、私的な感性、エッセイのような作品は、戦争や災害など混迷を深める世界で日常の忘れてはならない幸せや「かけがえのなさ」を想い出すものとして求められていくかもしれない。大きく変容するアートワールドの中で、ハイカルチャー・ポップカルチャー、アナログ・デジタルを横断した二人のコラボレーションが新たな歴史をどのように刻むのか期待が膨らむ。
文:三木学(美術評論家・色彩研究者)