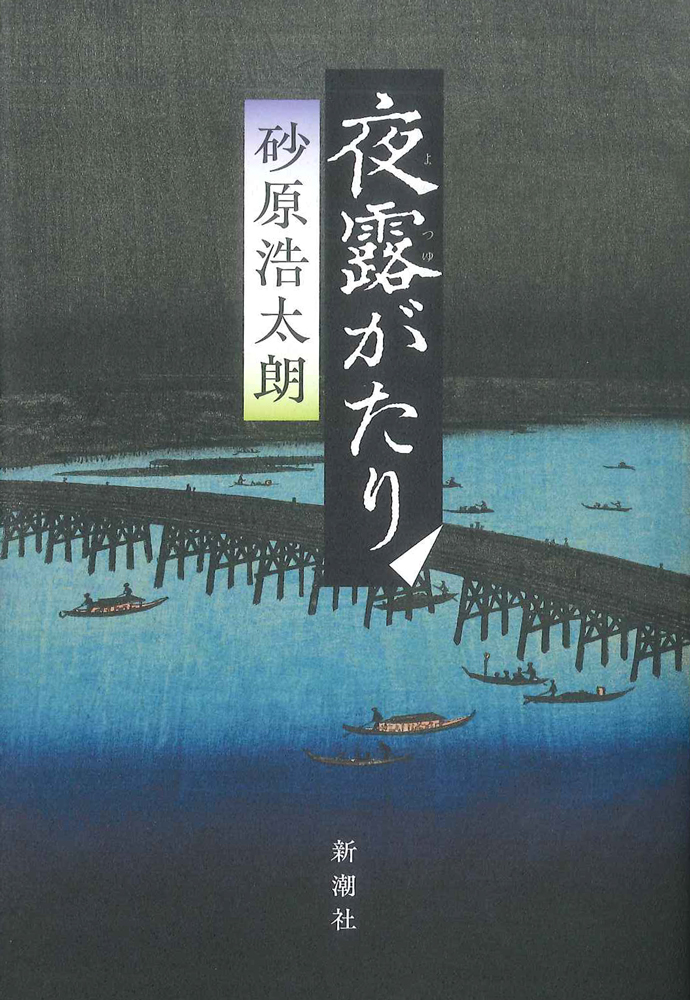【第267回】間室道子の本棚 『夜露がたり』砂原浩太朗/新潮社
「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。
本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。
本人のコメントと共にお楽しみください。
* * * * * * * *
『夜露がたり』
砂原浩太朗/新潮社
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
* * * * * * * *
テーマはまず、「橋を渡る」だと思った。庶民の移動がほぼ徒歩だった江戸時代、向こう岸まで行くことには意味や気持ちの切り替えがあったのだ。
両岸が暗示するのは現在と過去、華やかさと寂しさといった、相反するものが多いけれど、それだけだとお話が平面的になっちゃう。私の考えでは、本書の裏テーマは「一人足す」だ。砂原先生はそれがばつぐんにうまい。
たとえば、囲い者だった母親の死後、深川から対岸の日本橋、父・宗右衛門のいる美濃屋に引き取られた娘おるいの話がある。本妻はすでに亡くなっており、父は娘にやさしさや気遣いをたやさない。跡取りが確定している兄は十歳上で、宗右衛門が外につくった妹に関心はない。引き取られて二年、十八歳になるおるいには、小松屋への嫁入り話が舞い込んでいた。
そんな折、彼女は深川時代の男と再会する。自分は少女だったが体の関係があった。切れ長の瞳、いくらか高い頬骨。指物師になる夢をかなえた彼は、もうじき一本立ちだ、と照れくさそうに言った。おるいは嫁入り道具の文箱を男に依頼する。できあがった品を美濃屋に届けに来た別れ際、彼は彼女の手に小さな紙を押し付けた――。
この男が金持ちのお嬢さんになった幼馴染の幸せを願う善人でも腹に一物ある悪人でも、お話は平凡なものになるだろう。で、ここにおるいの結婚話の相手である小松屋の息子が絡む。「ライバル」ではない、複雑なかかわりかた。
別な一編には、今でいうギャンブル依存症の親に苦しめられている娘がでてくる。相模屋で働くおさとの前に、博打にはまり十年行方をくらませていた父・辰蔵があらわれた。奉公先はおくみに聞いたという。かつての長屋の隣人の、世話を焼きすぎる女だ。
父の借金を返すため働き続けた母は三年前に死んだ。今はおさとがそれを背負っている。冷たくあしらい別れて三日後、賭場の男が店に来た。
辰蔵がおととい大負けし、一両もの借金を作ったのだ。十年ぶりの江戸で、父によくご開帳の場所が、とおさとは思うが払えなければ自分が女郎になるしかない。
これだけだと、「毒親って江戸時代もあったんだ、人間って変わらないのね」で終わってしまうだろう。でも、れいの世話焼きのおくみが、物語にただならぬ作用をしている。
彼女が物語の半ばでおさとに見せる、「瞳の影のごときもの」、「この女が今まで見せたことのないたぐいのもの」、「面白がって、というようなものではなく、根深いなにかを感じずにはいられないもの」。
「柱となる人物を一名増やした」ではないの。建築でたとえるなら筋交(すじかい)。二本の柱のあいだに斜めにもう1本を加え、アルファベットの「N」のかたちをつくる。こうすると全体の強度が増すのだ。料理で言うならローリエ。煮込み料理に入れる葉っぱで、食材ではあるが食べ物ではないので途中で取り去られる。だが鍋全体にはおくみ、じゃなかったローリエが、最後まで漂っているのだ。
ほかにも「幼なじみ同士の三角関係」とか「貧乏な元藩士に降ってわいた人生のチャンス」とか、読者が想像しがちな展開になりそうな物語に一人足すことで、闇やコクが増す。そんな八編。おすすめです。
両岸が暗示するのは現在と過去、華やかさと寂しさといった、相反するものが多いけれど、それだけだとお話が平面的になっちゃう。私の考えでは、本書の裏テーマは「一人足す」だ。砂原先生はそれがばつぐんにうまい。
たとえば、囲い者だった母親の死後、深川から対岸の日本橋、父・宗右衛門のいる美濃屋に引き取られた娘おるいの話がある。本妻はすでに亡くなっており、父は娘にやさしさや気遣いをたやさない。跡取りが確定している兄は十歳上で、宗右衛門が外につくった妹に関心はない。引き取られて二年、十八歳になるおるいには、小松屋への嫁入り話が舞い込んでいた。
そんな折、彼女は深川時代の男と再会する。自分は少女だったが体の関係があった。切れ長の瞳、いくらか高い頬骨。指物師になる夢をかなえた彼は、もうじき一本立ちだ、と照れくさそうに言った。おるいは嫁入り道具の文箱を男に依頼する。できあがった品を美濃屋に届けに来た別れ際、彼は彼女の手に小さな紙を押し付けた――。
この男が金持ちのお嬢さんになった幼馴染の幸せを願う善人でも腹に一物ある悪人でも、お話は平凡なものになるだろう。で、ここにおるいの結婚話の相手である小松屋の息子が絡む。「ライバル」ではない、複雑なかかわりかた。
別な一編には、今でいうギャンブル依存症の親に苦しめられている娘がでてくる。相模屋で働くおさとの前に、博打にはまり十年行方をくらませていた父・辰蔵があらわれた。奉公先はおくみに聞いたという。かつての長屋の隣人の、世話を焼きすぎる女だ。
父の借金を返すため働き続けた母は三年前に死んだ。今はおさとがそれを背負っている。冷たくあしらい別れて三日後、賭場の男が店に来た。
辰蔵がおととい大負けし、一両もの借金を作ったのだ。十年ぶりの江戸で、父によくご開帳の場所が、とおさとは思うが払えなければ自分が女郎になるしかない。
これだけだと、「毒親って江戸時代もあったんだ、人間って変わらないのね」で終わってしまうだろう。でも、れいの世話焼きのおくみが、物語にただならぬ作用をしている。
彼女が物語の半ばでおさとに見せる、「瞳の影のごときもの」、「この女が今まで見せたことのないたぐいのもの」、「面白がって、というようなものではなく、根深いなにかを感じずにはいられないもの」。
「柱となる人物を一名増やした」ではないの。建築でたとえるなら筋交(すじかい)。二本の柱のあいだに斜めにもう1本を加え、アルファベットの「N」のかたちをつくる。こうすると全体の強度が増すのだ。料理で言うならローリエ。煮込み料理に入れる葉っぱで、食材ではあるが食べ物ではないので途中で取り去られる。だが鍋全体にはおくみ、じゃなかったローリエが、最後まで漂っているのだ。
ほかにも「幼なじみ同士の三角関係」とか「貧乏な元藩士に降ってわいた人生のチャンス」とか、読者が想像しがちな展開になりそうな物語に一人足すことで、闇やコクが増す。そんな八編。おすすめです。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ
間 室 道 子
【プロフィール】
雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『婦人画報』、『Precious』などに連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。