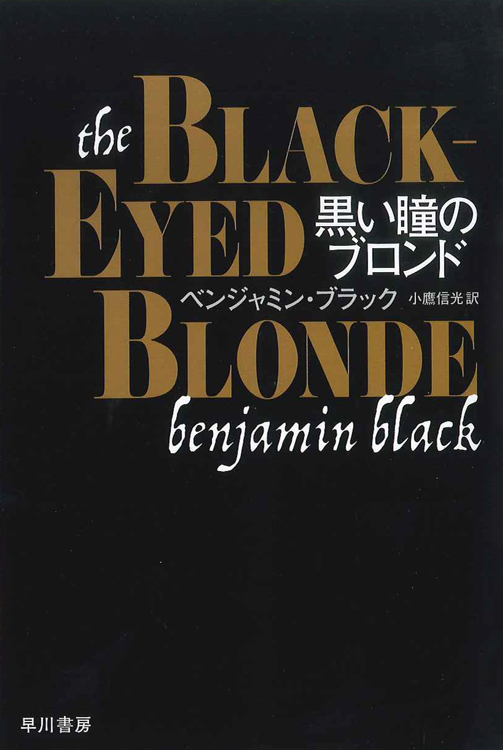【第234回】間室道子の本棚『黒い瞳のブロンド』ベンジャミン・ブラック 小鷹信光 訳/ハヤカワ文庫
「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。
本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。
本人のコメントと共にお楽しみください。
* * * * * * * *
『黒い瞳のブロンド』
ベンジャミン・ブラック 小鷹信光 訳/ハヤカワ文庫
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
* * * * * * * *
アイルランドの鬼才ベンジャミン・ブラックが書いた、レイモンド・チャンドラーの名作『ロング・グッドバイ』の続編。
金髪に黒い目、という非常にそそられる女が探偵マーロウの事務所で言い放ったのは、二カ月前に消えた私の愛人を見つけて、という依頼だった。美女の名はミセス・クレア・キャヴェンディッシュ。人妻である。しかも大金持ち。
というわけで歴代作品と同じく、事件の謎以上にマーロウを悩ませるのは女性たちだ。とくに本書では、今も胸の中にいる女とこれから深い関係になりそうな女が自分のいないところで自分の話をしていた、と聞かされた時の動揺シーンがたまらない。
「パシッと平手打ちをくらった感じ」と描写されているが、男性読者の多くは、そしてマーロウもあんなにタフでなければ、いやあああああ、やめてええええ、と耳と塞いでうずくまり、悶絶するところであろう。
閑話休題、依頼人クレアの小出しがすごい。愛人についてショッキングな事実をつかみ、お屋敷に出向いたマーロウは報告の途中で言葉をとぎらせ、まじまじと彼女を見るはめになる。クレアのほうは「謝ります。初めに申しあげるべきでした」と言ったあと、異様なことを明かす。
その後ふたりで広大な敷地内をお散歩(含む:キス)をしたあと、クレアはさらに驚くべきことを告げる。申し分のないさりげなさで。
読者もマーロウもぽかんとするしかない。「大人同士の駆け引きで女がうわ手」ではなく、探偵を「何をやってもヘマをしてしまう初めてのデートのガキになった気分」にしてしまうのだ。「どうも腑に落ちない」「まぎれもなく胡散臭い」とわかっているのに、探偵は黒い瞳のブロンドにのめりこんでいく。
「私は金で雇われる人間です」とビジネスライクなことも言うんだけど、「あれほどの女と縁を切るのはそうたやすいことではなかった」「彼女との仲を絶つことは私には出来ない」・・・契約であるはずの関係が、「縁」とか「仲」になっちゃってる!
でもこれはめろめろの証だけではない。女の向こうにあるものを探偵は本能で感じとっているのだろう。チャンドラーが描いてきた女性たちはマーロウをアップダウンさせ るがクレアはとくにひどい。というか一流中の一流だ。
彼のことが好きで、よく知っていて、こうすれば自分の掌で踊ってくれる、と確信を持ってるひと――。
本書は、生きているのに死んでるみたいな男たちと、死が下るなかひっそり息をしている男たちの物語でもある。マーロウは彼らに引っ張られないように手を伸ばすのだ、遠くの、あるいは目の前にいる、女たちが放ってくる愛に。だが・・・。
巻末解説の小山正さんは、クライマックスについて「賛否両論がありそう」と書いてるけど、私は「賛」である。で、物議をかもしたマーロウものといえば、ロバート・アルトマン監督の映画『ロング・グッドバイ』がある。
舞台が1950年代ではなく70年代に、マーロウが猫を飼ってる、半裸のオネエちゃんたちがうろうろ、アノ人が出てこないなど思いきった変更の中、最大のジャンプは「ふんわりしたどうしようもない人」を「はっきりとした悪党」にし、エリオット・グールド扮するマーロウがラストでそいつにあることをする。原作ファンにはブーイングだったらしいが私はこれも「賛」だった。おそらくベンジャミン・ブラックもそうなのではないか。
1973年のアルトマンの映画に、2014年、アイルランドからブラックが小説で「監督、俺もYESですよ」とラブコールを送った。そんな作品。待望の文庫化。
金髪に黒い目、という非常にそそられる女が探偵マーロウの事務所で言い放ったのは、二カ月前に消えた私の愛人を見つけて、という依頼だった。美女の名はミセス・クレア・キャヴェンディッシュ。人妻である。しかも大金持ち。
というわけで歴代作品と同じく、事件の謎以上にマーロウを悩ませるのは女性たちだ。とくに本書では、今も胸の中にいる女とこれから深い関係になりそうな女が自分のいないところで自分の話をしていた、と聞かされた時の動揺シーンがたまらない。
「パシッと平手打ちをくらった感じ」と描写されているが、男性読者の多くは、そしてマーロウもあんなにタフでなければ、いやあああああ、やめてええええ、と耳と塞いでうずくまり、悶絶するところであろう。
閑話休題、依頼人クレアの小出しがすごい。愛人についてショッキングな事実をつかみ、お屋敷に出向いたマーロウは報告の途中で言葉をとぎらせ、まじまじと彼女を見るはめになる。クレアのほうは「謝ります。初めに申しあげるべきでした」と言ったあと、異様なことを明かす。
その後ふたりで広大な敷地内をお散歩(含む:キス)をしたあと、クレアはさらに驚くべきことを告げる。申し分のないさりげなさで。
読者もマーロウもぽかんとするしかない。「大人同士の駆け引きで女がうわ手」ではなく、探偵を「何をやってもヘマをしてしまう初めてのデートのガキになった気分」にしてしまうのだ。「どうも腑に落ちない」「まぎれもなく胡散臭い」とわかっているのに、探偵は黒い瞳のブロンドにのめりこんでいく。
「私は金で雇われる人間です」とビジネスライクなことも言うんだけど、「あれほどの女と縁を切るのはそうたやすいことではなかった」「彼女との仲を絶つことは私には出来ない」・・・契約であるはずの関係が、「縁」とか「仲」になっちゃってる!
でもこれはめろめろの証だけではない。女の向こうにあるものを探偵は本能で感じとっているのだろう。チャンドラーが描いてきた女性たちはマーロウをアップダウンさせ るがクレアはとくにひどい。というか一流中の一流だ。
彼のことが好きで、よく知っていて、こうすれば自分の掌で踊ってくれる、と確信を持ってるひと――。
本書は、生きているのに死んでるみたいな男たちと、死が下るなかひっそり息をしている男たちの物語でもある。マーロウは彼らに引っ張られないように手を伸ばすのだ、遠くの、あるいは目の前にいる、女たちが放ってくる愛に。だが・・・。
巻末解説の小山正さんは、クライマックスについて「賛否両論がありそう」と書いてるけど、私は「賛」である。で、物議をかもしたマーロウものといえば、ロバート・アルトマン監督の映画『ロング・グッドバイ』がある。
舞台が1950年代ではなく70年代に、マーロウが猫を飼ってる、半裸のオネエちゃんたちがうろうろ、アノ人が出てこないなど思いきった変更の中、最大のジャンプは「ふんわりしたどうしようもない人」を「はっきりとした悪党」にし、エリオット・グールド扮するマーロウがラストでそいつにあることをする。原作ファンにはブーイングだったらしいが私はこれも「賛」だった。おそらくベンジャミン・ブラックもそうなのではないか。
1973年のアルトマンの映画に、2014年、アイルランドからブラックが小説で「監督、俺もYESですよ」とラブコールを送った。そんな作品。待望の文庫化。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ
間 室 道 子
【プロフィール】
雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『婦人画報』、朝日新聞デジタル「ほんやのほん」などに連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。